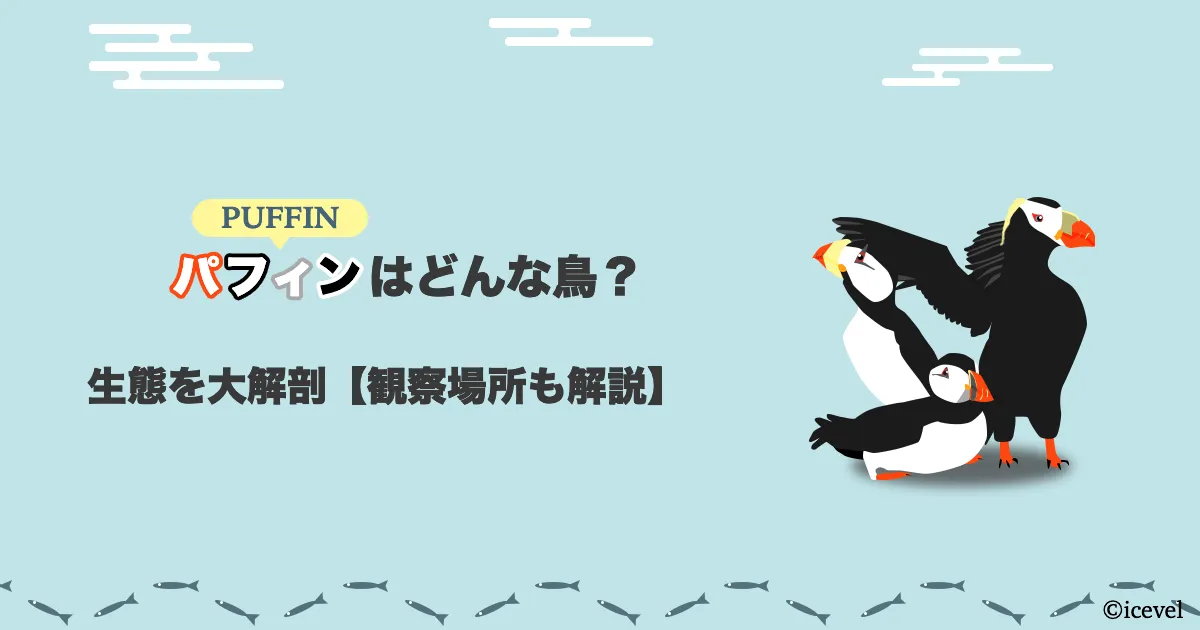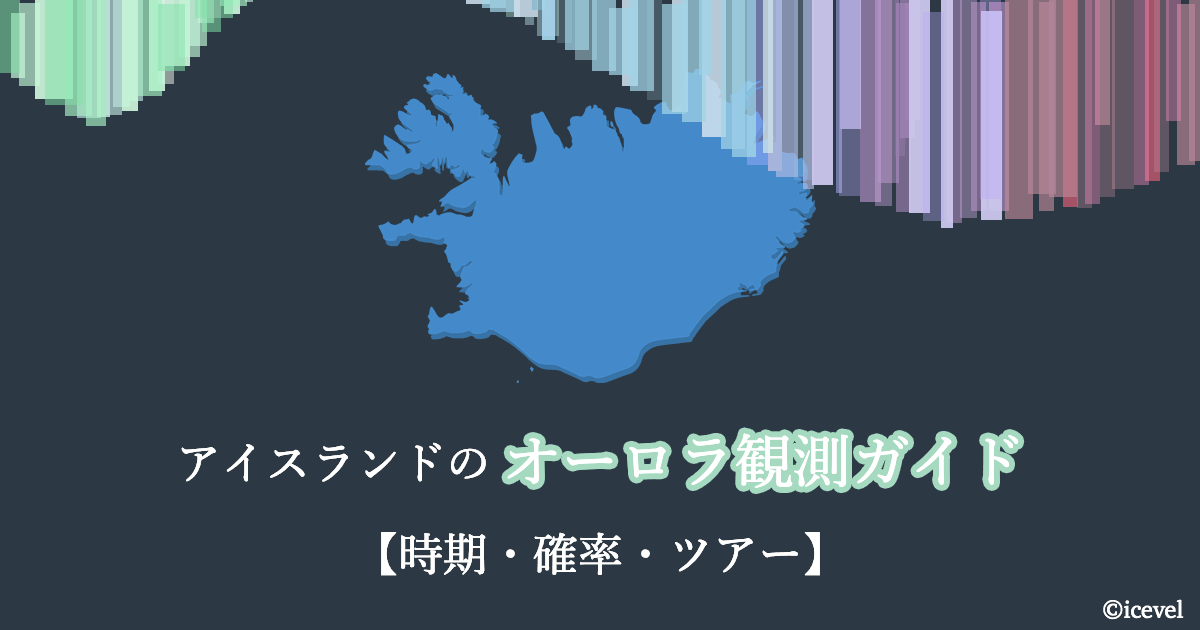こんにちは。
当サイトであるicevelを運営しているYamada(@icevel3)です。
日本でも可愛らしい見た目から人気の鳥「パフィン」。
「パフィンってどんな鳥なの?」
「どこでパフィンを見られるの?」
など、疑問や知りたいことがあると想います。
今回の記事では、3種類存在するパフィンの生態や観察できる国・地域、観察時の注意点などを解説しています。
※2024年6月9日:情報を更新しました
パフィンとはウミスズメ科の海鳥
パフィン(Puffin)とは、チドリ目ウミスズメ科に分類される海鳥です。
ずんぐりとした体型に白と黒の羽、オレンジの脚、大型の鮮やかなクチバシをしています。
パフィンの白い顔、鮮やかなクチバシ、脚などは春から夏にかけた繁殖期限定です。
繁殖期が終わる冬には顔が灰色になり、目やクチバシなどは地味な色になります。
パフィンは、その特徴的な外見から「海のピエロ」や「海のオウム」と呼ばれています。
また、パフィンの白黒の姿や直立姿勢からペンギンと間違えられることがありますが、まったく違う種類です。
パフィンという名前は「膨らむ」を意味する「Puff」が由来と考えられています。
羽毛は密集していて、丸く膨れ上がったような外見をしています。

パフィンは、海の冷たい北半球の高緯度地域に生息しています。
パフィンは3種類存在する
パフィンは、以下の3種類を総称します。
| パフィンの種類(和名) | 英名 | 学名 |
|---|---|---|
| ニシツノメドリ | Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
| ツノメドリ | Horned Puffin | Fratercula corniculata |
| エトピリカ | Tufted Puffin | Fratercula cirrhata |
パフィンの学名である「Fratercula」は、ラテン語で「小さな修道士」という意味です。
パフィンの見た目である、白と黒が修道士の衣服を連想させるだからそうです。
次からは、3種類のパフィンについて解説してきます。
ニシツノメドリ

ニシツノメドリは、日本でもっとも有名なパフィンです。
3種類のパフィンの中で、体長が小さいです。
春からの繁殖期になると、ニシツノメドリの顔は白くなり、クチバシや脚が鮮やかな色になります。
ニシツノメドリは主に北大西洋に生息しているので「大西洋のツノメドリ」と名前が付いたといわれています。
| 体長 | 32cmほど |
|---|---|
| 体重 | 約500g |
| 分布 | 北大西洋〜北極海 |
| アイスランド、スカンジナビア半島、 グリーンランド、イングランド・スコットランド、 北フランス、カナダ、北アメリカ東部 |
ツノメドリ

ツノメドリは、ニシツノメドリと外見が似ているパフィンです。
この2種類の違いはクチバシです。
ツノメドリのクチバシの付け根は黄色や灰色をしていて、ニシツノメドリのクチバシの付け根は黄色をしています。
さらに、ツノメドリは春からの繁殖期になると、目の上に尖った突起物が現れます。
目の上に尖った突起物から、ツノメドリを漢字で書くと「角目鳥(つのめどり)」です。
ツノメドリの英名「Horned Puffin」の由来は、目の上にある突起物の「Horn=角」からきています。
| 体長 | 38cmほど |
|---|---|
| 体重 | 約600g |
| 分布 | 北太平洋 |
| 千島列島、ロシアのカムチャッカ半島、 アラスカの海岸線沿い |
エトピリカ

エトピリカは、3種類のパフィンの中で体長が大きい海鳥です。
エトピリカは春からの繁殖期になると、顔が白くなったりクチバシや脚が色鮮やかになります。
さらに、目の上にかけて金色の飾り羽が生えてくるのが特徴的です。
繁殖期が終わる冬には顔が灰色になり、飾り羽も抜けます。
ツノメドリとニシツノメドリは胸やお腹部分が白の羽毛ですが、エトピリカは顔と脚以外が黒の羽毛に覆われます。
エトピリカという名前はアイヌ語が由来で「エトゥ(くちばし)ピリカ(美しい)」という意味です。
特徴的な外見から、別名「花魁鳥(おいらんどり)」とも呼ばれています。
| 体長 | 44cmほど |
|---|---|
| 体重 | 約700g |
| 分布 | 北太平洋 |
| 北海道東部〜千島列島、ロシアのカムチャッカ半島、 アラスカ〜カルフォルニアの海岸線沿い |
パフィンの生態
パフィンの特徴的な生態を紹介していきます。
飛行能力はあまり高くない

パフィンは体の大きさに対して翼が小さいので、飛行能力はあまり高くありません。
空を飛ぶために1分間で300回〜400回も羽ばたき、最大88kmの速さで飛ぶことができます。
パフィンは海面から空へ飛び立つとき、助走をしながら水の上を走ります。
また、パフィンは着陸や着水が苦手です。
具体的には、海面にぶつかりながら着水、草の上にゴロゴロ転がりながら着陸、仲間のパフィンに衝突しながら着陸します。
1年のほとんどを海で暮らす

パフィンは1年のうち、約8ヶ月を海で生活する海鳥です。
一般的に4月中旬からコロニーがある地上に戻り、8月末までには再び海に帰って越冬します。
パフィンは、水上での生活に適応しています。
羽毛は防水に優れ、海水を飲んで余計な塩分を鼻腔の腺から排出することが可能です。
パフィンは、かならずしもパートナーと一緒に海で過ごすとは限りません。
繁殖期が始まる春の季節には陸でパートナーと再会し、クチバシをぶつけ合う求愛行動をします。
飛ぶように水中を泳ぐ
パフィンは、泳ぎが得意な海鳥です。
水中では翼を羽ばたかせて泳ぎ、脚で泳ぐ方向を調整しています。
パフィンの主食はニシンやシシャモ、サンドウナギなどの小魚です。
パフィンの泳ぐスピードは時速26kmほどで、潜水時間は約20秒〜30秒ほどです。
魚を狩りするときには、約60mの深さまで潜れます。
一度に魚を何匹もくわえる

パフィンは、一度に複数の小魚を巣穴に持ち帰ることができます。
一度にくわえられる小魚の数は平均10匹ほどですが、過去に100匹以上の小魚を一度にくわえたパフィンの記録があります。
パフィンのクチバシの裏には、とげのような返しがあって、一度に多くの魚を捕まえることが可能です。
パフィンのヒナが生まれると、親鳥は子供ために海で小魚を捕まえて巣穴に届けます(何度も往復します)。
穴を掘ってヒナを育てる

パフィンは、卵を守るために地面の下や岩の隙間に巣穴を作る海鳥です。
巣穴はクチバシを使って穴を掘り、脚で土をかき出します。
また、ウサギが掘った穴を巣穴として再利用することも。
パフィンは通常1年に1個の卵を産み、両親が温めながら育てます。
孵化したパフィンのヒナには別名があり、パフリング(Pufflings)です。
パフィンの寿命は約20年ほどで、一度作った巣穴は何年も同じパフィンが使用します。
パフィンは一夫一婦制で、基本的にパートナーと一生添い遂げるといわれています。
パフィンの観察はアイスランドが最適
北ヨーロッパの北大西洋上に位置するアイスランドは、パフィンの観察に適した国です。
ニシツノメドリの約60%は、アイスランドで繁殖するといわれています。
ニシツノメドリがアイスランドで見られる時期は、4月下旬から8月下旬ぐらいです。
アイスランドでニシツノメドリを観察するのに最適なスポットは、以下のとおりです。
- ウエスマン諸島
- ディルホゥラエイ
- ラゥトラビャルグ
- アークレイ島・ランディ島
ウエストマン諸島
ウェスマン諸島(Vestmannaeyjar)は、アイスランドの南海岸沖にある15の島と30の岩山からなる群島です。
アイスランドの中でもウェスマン諸島は、ニシツノメドリが多く集まる世界最大のコロニーになります。
ウェスマン諸島でニシツノメドリの観察に適しているのは、ヘイマエイ島(Heimaey)にあるStórhöfðiという場所です。
ヘイマエイは、ウェスマン諸島で唯一の人が住んでいる大きい島です。
島の最南端にはStórhöfðiという半島があり、ここにニシツノメドリのコロニーがあります。
Stórhöfðiにはバードウォッチング用の小屋があり、そこからニシツノメドリをはじめ、さまざまな野鳥の観察ができます。
ヘイマエイ島へ行くにはフェリーが最適です。
アイスランドの本土にあるLandeyjahöfnという港とウェスマン諸島を結ぶフェリーが1日7回出ています。
Stórhöfðiはヨーロッパでも風が強い場所なので、夏でも暖かい服装にしていきましょう。
ディルホゥラエイ
ディルホゥラエイ(Dyrhólaey)は、アイスランド南部の海岸にある岬の名前です。
岬の崖にはニシツノメドリをはじめ、さまざまな野鳥のコロニーがあります。
海に突き出たディルホゥラエイの高さは約120mで、アーチ状の岩が特徴的です。
首都のレイキャビクからディルホゥラエイまでは、車で約2時間半ほどかかります。
野鳥の繁殖シーズンである5月と6月には、ディルホゥラエイへいく道が制限されているかもしれません。
日中(9時〜18時)であれば、ディルホゥラエイの上まで徒歩でいけます。
ラゥトラビャルグ
ラゥトラビャルグ(Látrabjarg)は、アイスランドの西部フィヨルド地方にある岬の名前です。
岬の崖には、ニシツノメドリのコロニーがあります。
ラゥトラビャルグは、アイスランドで多くの野鳥が見られるスポットの一つです。
崖の高さは最大441mで、長さは14kmもあります。
首都のレイキャビクからラゥトラビャルグまでの距離は、約430kmで車だと約6時間ほどかかります。
また、西部フィヨルドにあるビルドダール空港(Bíldudalur Airport)からラゥトラビャルグまでの距離は、約90kmで車だと約1時間半ほどです。
飛行機で行く西部フィヨルドツアー(1泊2日)に参加すれば、ツアーガイドがラゥトラビャルグへ連れてってくれます。
アークレイ島・ランディ島
アークレイ島(Akurey)とルンディ島(Lundi)は、アイスランド西部のファクサ湾にある小さな島です。
繁殖期になると、2つの島にニシツノメドリがやってきます。
アークレイ島とルンディ島は、アイスランドの首都であるレイキャビクから近い距離にあります。
レイキャビクから船で行くパフィンツアーが開催されているので、レンタカーを借りないでニシツノメドリを見たい方におすすめです。

アイスランド語でパフィンは、Lundi(ルンディ)と呼ばれています!
その他パフィンが見られる国・地域
アイスランド以外にも、パフィンの観察に適した場所があります。
- スコットランド(イギリス)
- イングランド(イギリス)
- アイルランド
- アラスカ(アメリカ)
- 北海道
パフィンの観察ができる国や地域を解説していきます。
スコットランド(イギリス)
イギリスの北部にあるスコットランドでは、ニシツノメドリを見られるスポットが多くあります。
スコットランドにある離島の沖合には、ニシツノメドリのコロニーがあります。
ニシツノメドリが見られてアクセスしやすいところは、メイ島(May Island)やクレイグリース島(Craigleith island)などです。
メイ島とクレイグリース島は、スコットランド東部のフォース湾にある島です。
2つの島には海鳥が数多く生息しており、湾内や島は国の自然保護区に指定されています。
ニシツノメドリがメイ島やクレイグリース島へやってくる時期は、4月から8月中旬ぐらいです。
スコットランドの本土からメイ島までは約8km離れていて、フェリーやボートで島へ上陸できます。
スコットランドの首都であるエジンバラまたはアンストライザーから、メイ島・クレイグリース島までフェリーやボートが出ています。
イングランド(イギリス)
ロンドンがあるイングランドでは、ニシツノメドリを見られるスポットがあります。
イングランド本土でニシツノメドリが見られてアクセスしやすいところは、ベンプトン・クリフ(Bempton Cliffs)です。
ベンプトン・クリフは、ヨークシャー地方のイースト・ライディングにある断崖絶壁の海岸です。
イングランドで多くの海鳥が集まる場所で、RSPB(英国王立鳥類保護協会)が自然保護区として管理しています。
ニシツノメドリは繁殖期になると、イースト・ライディングの断崖絶壁に巣を作ります。
ニシツノメドリがベンプトン・クリフへやってくる時期は、4月中旬から7月中旬ぐらいです。
ロンドンからベンプトン・クリフまでの距離は約380kmほどです。
アイルランド
西ヨーロッパに位置するアイルランド(Irelland)の西海岸では、ニシツノメドリが見られます。
アイルランドでニシツノメドリのコロニーがある有名な島といえば、スケリグ・ヴィヒール(Skellig Michael)になります。
スケリグ・ヴィヒールは、アイルランド南西の沖にある世界文化遺産に登録されている島です。
島は、映画「スター・ウォーズ」のシリーズ「フォースの覚醒(2015年)」「最後のジェダイ(2017年)」「スカイウォーカーの夜明け(2019年)」のロケ地としても有名です。
作中に登場するルーク・スカイウォーカーが隠居生活を送っていた島のロケ地がスケリグ・ヴィヒールです。
また、映画内に登場するポーグ(Porg)というキャラクターのモデルは、パフィンとスター・ウォーズ側が述べています。
ニシツノメドリがスケリグ・ヴィヒール島へ滞在する期間は、4月から8月下旬ぐらいです。
スケリグ・ヴィヒール島の近くへ行くには、ボートツアーを利用しましょう。
毎年4月から9月末ごろ、ケリー州のポートマギーという村からスケリグ・ヴィヒールへのボートツアーが開催されています。
日本からアイルランドの直行便はありませんが、イギリス(ロンドン)経由で行くのがおすすめです。
アラスカ(アメリカ)
アメリカ合衆国の最北端にあるアラスカ州では、ツノメドリやエトピリカの2種類が見られます。
アラスカでツノメドリやエトピリカが見られてアクセスしやすいところは、キーナイ半島(Kenai Peninsula)です。
キーナイ半島はアラスカ州の南部に位置しており、半島内には氷河やフィヨルドが広がるキーナイ・フィヨルド国立公園があります。
キーナイ半島にあるビーハイブ島(Beehive Islands)やチルウェル諸島(Chiswell Islands)の崖には、パフィンのコロニーがあります。
キーナイ半島で開催されているクルーズツアーを利用すると、パフィンやクジラなどの野生動物や氷河を回ることが可能です。
北海道でもパフィンを見れる
北海道では、パフィンのエトピリカとツノメドリを見れることがあります。
以前まで、北海道東部の島にエトピリカが訪れていましたが、1970年代からエトピリカの数は減少傾向にあります。
現在では、根室市にある無人島のユルリ島やモユルリ島などで数組のつがいが確認されているのみです。
環境省では、エトピリカを絶滅危惧種ⅠA分類(レッドリスト)に分類しています。
エトピリカが北海道に訪れる時期は、4月下旬から8月下旬ぐらいです。
一般人がユルリ島やモユルリ島へ上陸することは基本的にできません。
ただし、島を回るクルーズツアーを利用すれば、エトピリカを見られるかもしれません。
一方、ツノメドリは根室沖や知床沖にやってくることがあります。
冬の時期に北海道へやってきますが、過去には夏に目撃例があります。
日本の動物園や水族館でパフィンを見られることも
日本の動物園や水族館には、パフィンを飼育しているところがあります。
| 飼育している動物園・水族館 | |
|---|---|
| ニシツノメドリ | 那須どうぶつ王国(栃木県) |
| エトピリカ | 鴨川シーワールド(千葉県) 葛西臨海水族園(東京都) ふくしま海洋科学館(福島県) 大阪海遊館(大阪府) |
パフィンのいる動物園や水族館の最新情報は、日本動物園水族館協会の公式サイトにある飼育動物検索をご覧ください。
パフィンを観察するときの注意点
野生のパフィンを観察するときには、以下に注意しましょう。
- マナーを守って観察する
- 暖かい服装で観察する
- 双眼鏡やカメラがあるとよい
マナーを守って観察する
パフィンに限らず、野生動物を観察するときには以下のマナーを守りましょう。
- 巣に近づかない
- パフィンを直接触れようとしない
- エサを与えない
- 自然を傷つけないように指定された道を歩く
- ゴミは持ち帰る
パフィンに近づくときには、姿勢を低くしてゆっくりと動きましょう。
また、場所によってパフィンのいる崖には柵が設置されていない場合があるので、落ちないように注意しましょう。
暖かい服装で観察する
野生のパフィンを観察するときには、暖かい服装を選びましょう。
パフィンのコロニーがある海岸には風を遮るものがほとんどなく、海水で服が濡れるかもしれません。
そのため、野生のパフィンを観察するときには防水や防風機能のある上着、濡れたとき用に替えの服などがあるとよいでしょう。
ほかにも、紫外線対策で帽子や日焼け止めを用意するのもおすすめです。
双眼鏡やカメラがあるとよい
パフィンをはじめ、野鳥を観察や記録に残したい場合は、双眼鏡やカメラがあると便利です。
双眼鏡は倍率8〜10倍が使いやすく、防水性能があると安心です。
カメラの望遠レンズは、焦点距離が300mm(35mm換算)以上はあるとよいでしょう。
カメラやレンズなど重い機材を持っていきたくない場合は、カメラとレンズの一体型でコンパクトなコンデジの防水タイプがおすすめです。
【まとめ】パフィンは見た目もかわいい海鳥
海鳥のパフィンについて解説をしました。
今回の記事をまとめると、以下になります。
- パフィンは、ずんぐり体型と鮮やかなクチバシのある海鳥
- パフィンには「ニシツノメドリ」「ツノメドリ」「エトピリカ」の3種類が存在する
- パフィンは1年のほとんどを海で生活し、4月〜8月の繁殖期には陸へやってくる
- ニシツノメドリの約60%はアイスランドで繁殖するので、パフィンの観察に適している
- スコットランド、イングランド、アイルランドはニシツノメドリの観察に適している
- アラスカではツノメドリやエトピリカの2種類が見られる
- 北海道の根室市にある無人島にはエトピリカがやってくる
- 野生のパフィンを観察するときにはマナーを守ること
パフィンを観察しに、旅行計画を立ててみてはいかがでしょうか?